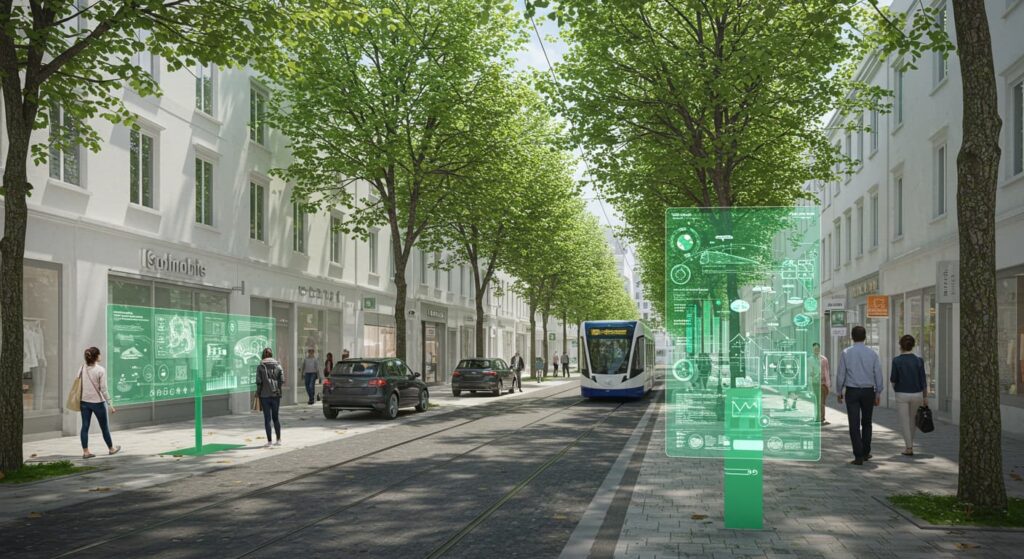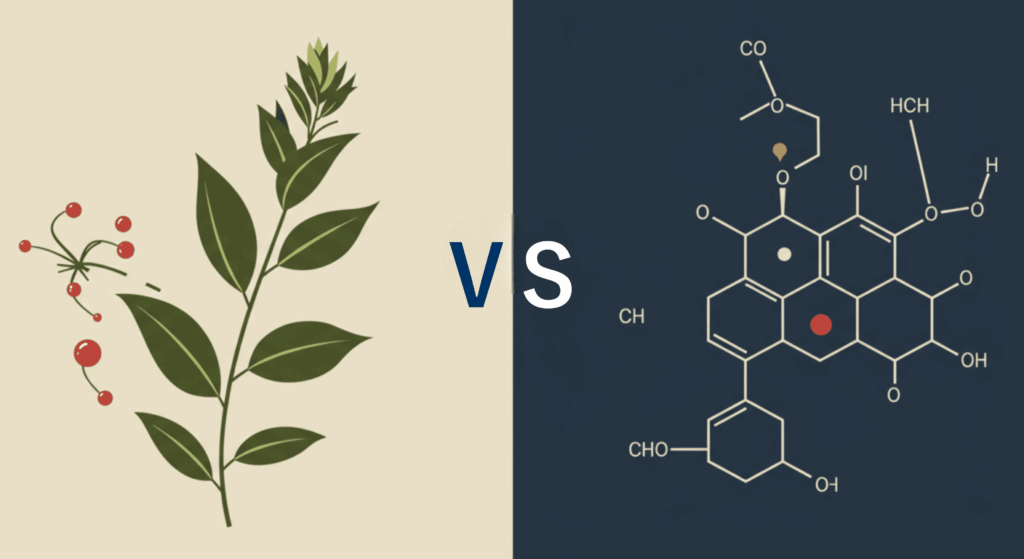新素材開発:R&D予算と社会実装費は別物である。研究開発と社会導入の間に潜む「死の谷」を越えるために
2025-08-30

素材や新技術は、研究開発が成功しただけでは社会に広がりません。現場で使える形に落とし込むには「社会実装費」という独自の費用が必要です。本稿では、供給者と需要者の評価ギャップ、R&Dと実装コストの違い、海外での議論を整理し、社会実装費を明示的に位置づける重要性を考えます。
供給サイドと需要サイドのすれ違い
新素材の導入を阻む最初の壁は、供給者と需要者の間にある評価の分断です。供給側は一般的な物性試験までで止まり、需要側は用途ごとの試験を求めます。この非対称性が導入ハードルを高め、結果的に「死の谷」の温床となっています。
一般的物性試験にとどまる供給サイド
素材メーカーは多くの場合、ISOやJISといった標準規格に基づく「一般的物性試験」までを行います。これにより強度や耐熱性といった基礎データは得られますが、それはあくまでカタログ的な情報に過ぎません。
一般的物性試験とは
標準規格に基づき、素材そのものの性質を横断的に把握する試験。材料の“パスポート”として、研究や品質管理で広く使われます。

用途ごとの検証を求める需要サイド
一方でユーザー企業は、実際の使用環境を模した「用途ごとの物性試験」を必要とします。自動車分野であれば耐摩耗や温度サイクル、医療分野であれば薬液耐性など、現場固有の条件での性能が問われます。供給側がそこまで踏み込まない場合、需要者が自ら高額な追加試験を行う必要があり、導入ハードルが跳ね上がります。
用途ごとの物性試験とは
実際の使用条件に即した評価試験。自動車、医療、建材など、それぞれの現場条件を再現し、規格合否や性能改善を直接確認します。
用途開発の逆ベクトル構造

標準規格に基づく一般的物性試験は横断的な比較に有効ですが、用途ごとの物性試験がなければ導入は進みません。両者の違いを整理することが社会実装の第一歩となります。
ユーザーにとっての性能向上
前者は初期検討の基礎材料となりますが、後者がなければ実際の導入は進みません。実用化が進むほど、供給サイドも用途別試験を担う責任を負うようになります。
研究成果と市場ニーズのすれ違い

供給者は抽象的な物性データにとどまりがちで、需要者は具体的な改善効果を求めます。この逆方向のベクトルが、提供価値を散漫にし、結果として研究成果と市場ニーズのすれ違いを生み出しています。
基礎にとどまる供給者
研究者は基礎物性や論文的説明に重きを置きます。「強度が〇%向上」といった数値は科学的に価値がある一方で、顧客にとっては意思決定に直結しません。
用途の具体特性を求める需要者
需要側が求めるのは「エンドプロダクトのどの性能がどう改善されるか」という具体的な答えです。ニーズは理屈ではなく、改善そのもの、すなわち現場での解決策です。
「死の谷」の温床
研究成果が実用化に至らない理由の一つは、この試験ギャップにあります。研究側は「データを出せば通じる」と考えがちですが、現場は「直感的に安心できる具体性」を求めます。両者の間に横たわる距離は想定以上に大きいのです。
提供価値が散漫になる
基礎データが具体的価値に翻訳されないと、成果は“散漫”に見えます。結果として供給者の主張と顧客の期待がすれ違い続けるのです。
R&D費と社会実装費を分ける必要性
研究費と実装費は本質的に異なるものです。実装科学の議論では、導入のための費用を研究費とは切り離して計上すべきとされます。過小評価されがちな実装コストを可視化することが「死の谷」を越える唯一の道筋です。
実装科学の視点
実装科学(Implementation Science)の研究分野では、研究開発費と社会実装費は明確に区別すべきだとされています。社会実装にはトレーニング、インフラ整備、利害関係者との調整など独自のコストが発生するからです(Damschroder et al., Implementation Science, 2009)。
実装コストの過小評価

複数の研究では「実装コストは経済評価に十分反映されず、資金計画から抜け落ちやすい」と指摘されています(Hoomans & Severens, Implementation Science Communications, 2014)。現場導入に必要な費用が軽視され、資金ギャップが生じるのです。
研究費とは別建てで計上すべき領域
米国の議論では、実装前の計画立案や戦略設計、調整といった段階にも相応の費用がかかるとされています。
研究費とは別建てで計上すべき領域です。
RAND研究所などの政策レポートは、助成金設計において「実装と持続化」を視野に入れ、準備費や初期導入資金を確保すべきだと明言しています。
見過ごされがちなフィードバックループ
社会実装は需要サイドと供給サイドの中間に位置し、試作検証のフィードバックループが何度も繰り返されるべき領域です。しかし、コストも時間も過少に見積もられがちなため、ここに専用予算を設定することが不可欠です。
まとめ:
研究成果を社会に根づかせるためには、研究費だけでなく「実装のための投資」を制度的に確保することが欠かせません。R&Dと社会実装費の峻別は、新素材・新技術を真に社会に届ける第一歩になり得ます。
社会実装費の意味
- R&D費と社会実装費は性格が異なり、別枠で扱う必要がある
- 実装費は軽視・過小評価されやすく、死の谷を越える最大の障害となっている
- 小規模実証や初期導入こそが社会実装への最大の効果を生む
- 政策や経営判断では「社会実装費」を明示的に設けることが必須である

出典
- Damschroder LJ, et al. “Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework.” Implementation Science. 2009.
- Hoomans T, Severens JL. “Economic evaluation of implementation strategies.” Implementation Science Communications. 2014.
未来をともに形にしませんか
新素材の社会実装に関心をお持ちの方、実証や用途開発にご興味のある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。小さなご相談からでも歓迎いたします。
この記事を共有する