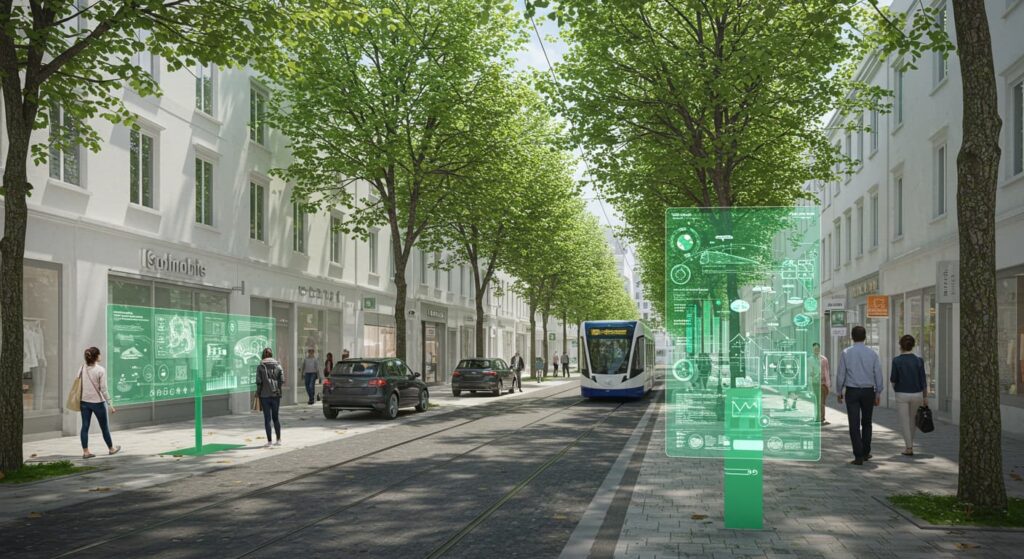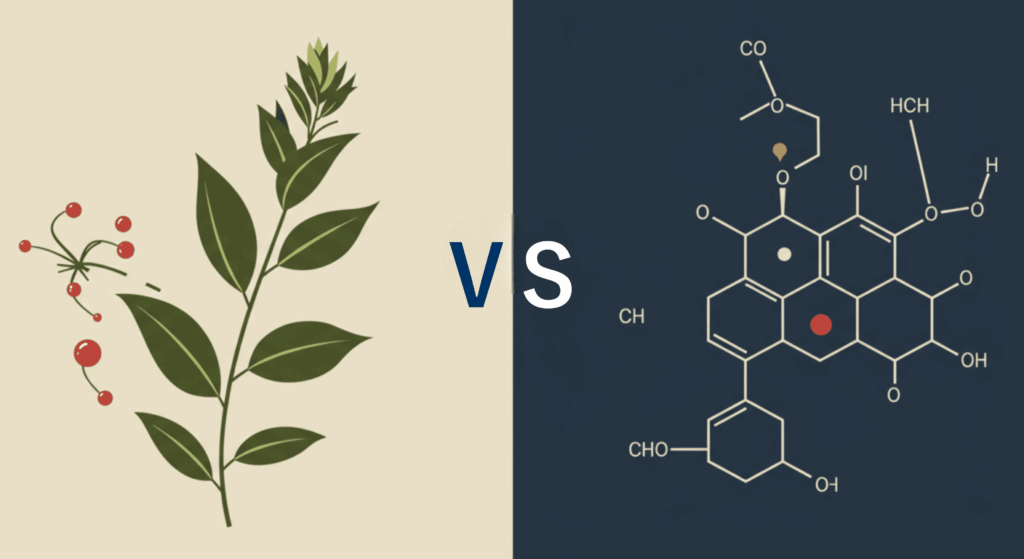EU規制文書「Reg. 2024/1257」はタイヤ摩耗粉じんの排出を初めて法的に規制し、ICCT報告書はその科学的根拠と政策提言を補足、WP.29技術文書は測定法と試験条件の国際標準化を進める役割を担います。
EUタイヤ粉じん規制の最新動向
2025-05-12

「Regulation (EU) 2024/1257(Euro 7)」は、タイヤやブレーキの摩耗による粉じん排出を新たに規制対象とすることで、環境汚染への対策を強化しています。これにより、自動車メーカーやタイヤメーカーは、新たな技術開発や製品改良が求められることになります。日本を含む他の地域でも、今後同様の規制が導入される可能性があり、国際的な動向に注目が集まっています。
Euro 7とは?
EUでは、タイヤの摩耗によって年間45万トンのマイクロプラスチックが発生しており、これは塗料に次いで2番目に多いマイクロプラスチックの発生源とされています。これらの微粒子は空気中や水中に拡散し、環境や人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。EUは、2030年までにマイクロプラスチックの排出量を30%削減することを目標としており、タイヤ摩耗粉じんの規制はその達成に向けた重要な施策の一つと位置付けられています。
ポイント
- EUが2024年に採択した新しい車両環境規制。
- 従来のEuro 6(乗用車・小型商用車)およびEuro VI(大型車)を統合。
- 排出ガスに加え、ブレーキ・タイヤの非排気粒子(PN)を新たに規制対象に含む。
タイヤ摩耗粉じんの影響
| 影響領域 | 影響の種類 | 詳細内容 |
| 大気汚染 | 主目的(直接) | PM10・PM2.5などの吸入性粒子として都市部の大気質を悪化させ、呼吸器疾患などの健康リスクを高める。 |
| 海洋環境 | 副次的(間接) | 路面の粉じんが雨水経由で河川・海へ流出し、マイクロプラスチックとして海洋生物に蓄積・影響を与える。 |
| 土壌汚染 | 副次的 | 路肩などに堆積し、微生物や植物の根への悪影響が懸念される。 |
| 水資源への影響 | 副次的 | 一部の粒子が浄水処理をすり抜けて水道水や地下水に混入する可能性がある。 |
| 生物多様性 | 副次的 | 微粒子の摂取により、水生生物や陸上動物の生態系や食物連鎖に悪影響を及ぼす。 |
| 都市清掃・管理負担 | 副次的 | 路面の粉じん除去など、自治体の清掃業務・インフラ維持コストが増大する。 |
タイヤ摩耗粉じんの排出上限値
タイヤ分類 | 排出上限値(mg/km) | 備考 | 型式認証適用開始 | 市販・装着全面義務 |
C1 | 3 mg/km | 乗用車用タイヤ | 2028年7月1日 | 2030年7月 |
C2 | 5 mg/km | 小型商用車用タイヤ | 2030年4月1日 | 2032年4月 |
C3 | 7 mg/km | 大型商用車用タイヤ | 2032年4月1日 | 2034年4月 |
ポイント
- タイヤ摩耗粉じんの測定方法自体がまだ国際標準化(UN WP.29)途上であり、具体的な数値規制の設定には技術的合意が必要。
- EUでは、今後の技術進展と産業界の合意をもとに、2026年ごろから段階的に排出限度値を設定予定。
- 実際の数値規制案は、ICCTレポートやETRMA(欧州タイヤ製造者協会)が先行して提示している。
摩耗粉じんの測定方法
対象はC1〜C3タイヤの摩耗粒子(PM)です。
室内ドラム試験:主要な型式認証用測定手法
ドラム上でタイヤを回転、質量損失を測定。この方法は、試験の再現性と効率性に優れており、実際の走行条件との相関性も高いとされています。
試験装置:摩耗性の高いドラム上でタイヤを回転させ、摩耗量を測定します。
走行距離:約5,000 km相当の走行をシミュレーションします。
測定項目:タイヤの質量損失を測定し、摩耗率を算出します。
屋外走行試験:補完的または将来的な監査用途として
実車による8,000km走行で質量変化を測定。この方法は、タイヤの実際の使用条件を反映した摩耗データを取得するために有効とされています。
試験構成:4台の車両によるコンボイ走行を実施し、1台に基準タイヤ、他の3台に候補タイヤを装着します。
走行距離:8,000 kmを走行し、500 kmごとに車両とドライバーの組み合わせを変更します。
目的:多様なタイヤサイズ、パターン、ブランドから摩耗データを収集し、市場評価を行うことを目的としています。
UNECE WP.29によって開発された試験方法
国連自動車基準調和世界フォーラム(UNECE WP.29)によって開発された、タイヤの摩耗粉じん(マイクロプラスチック)排出量を評価するための標準化された試験方法です。この方法は、特にC1クラス(乗用車用)タイヤを対象としており、Euro 7規制やUN規則第117号への適合性評価に使用されます。
試験概要
試験装置:直径1.7m以上の外部ドラムを備えた試験機を使用します。
負荷:タイヤの負荷指数(LI)の80%
空気圧:標準ロードタイヤは210kPa、強化タイヤは250kPa
走行速度:直線区間で100km/h、カーブ・勾配区間で60km/h
走行距離:1サイクル250kmを20回繰り返し、合計5,000km
ドラム表面:砂や石などで構成され、ISO 13473-1に基づく平均プロファイル深さ(MPD)とマイクロラフネスが規定されています。
測定・評価項目
質量損失:試験前後のタイヤ質量を測定し、摩耗量を算出します。
摩耗率:質量損失を走行距離とタイヤ負荷で正規化し、mg/km/tの単位で表します。
摩耗指数(AICT):候補タイヤの摩耗率を標準参照タイヤ(SRTT)と比較して算出します。
規定文書
EUR-Lex(Reg. 2024/1257) :法的枠組みのみ明記
|
発行主体 |
欧州連合(EU) |
|
文書の性質 |
法令(Regulation)そのもの |
|
内容の特徴 |
公式かつ拘束力のある規定。法的義務の根拠。 |
|
使用用途 |
官報、法務・規制遵守、認証機関向け文書。 |
ICCT報告書(ID-116):政策評価と提言
|
発行主体 |
ICCT(International Council on Clean Transportation) |
|
文書の性質 |
解説・評価レポート |
|
内容の特徴 |
法規の背景、インパクト分析、技術評価、他国比較などを分かりやすく解説。 |
|
使用用途 |
研究者、企業の政策部門、NGO、メディア、政策提言など。 |
UN WP.29技術文書:測定方法および試行値等
|
目的 |
各国の自動車規制を調和させるための技術基準・試験方法の国際標準化 |
|
対象文書 |
UN規則(UN Regulations)、世界技術規則(UN GTR)、作業文書(Informal Docs)など |
|
作成主体 |
WP.29配下の分科会(例:GRBP=騒音・タイヤ、GRPE=排ガス等)と技術専門家グループ(TFs) |
|
役割 |
各国の型式認証制度や規制(例:EUのEuro規制)への技術的根拠や測定手法を提供 |
規定機関
UNECE WP.29は、規制そのものを決定する政府主導の公式な国際会議体であり、一方のICCTは、その規制内容を科学的・データ的な観点から支える独立系の分析機関です。両者の関係は、WP.29が制度設計者、ICCTがその設計支援チームのような位置づけであり、ICCTは信頼性の高い科学的エビデンスを提供する民間パートナーとして、継続的な連携を図っています。
UNECE WP.29とICCT
|
|
UNECE WP.29 |
ICCT |
|
設立母体 |
国連欧州経済委員会(United Nations Economic Commission for Europe) |
非営利シンクタンク(米国本拠) |
|
機能 |
世界共通の車両法規(UN規則)を策定・採択する政府間枠組み |
各国の交通・排出規制に対する科学的分析・政策提言を行う民間組織 |
|
対象 |
規制(UN R117など)、技術基準、型式認証、測定方法 |
規制のインパクト評価、削減ポテンシャル分析、データモデル化 |
|
構成 |
国家政府・規制当局・自動車技術作業部会(GRBP等) |
分析官・研究者・環境政策専門家など民間主体 |
|
成果物 |
法的拘束力を持つUN規則・補足規定 |
政策レポート・評価モデル(例:Euro 7報告書ID-116) |
WP.29は“国連主導”であって“欧州ローカル”ではない
WP.29は“欧州発祥”ではありますが、“国際協調と多国間技術調和”を前提とした国連主導の自動車基準統一プラットフォームです。欧州は中心的なプレイヤーの一つではあるものの、日本、アメリカ、中国、韓国、カナダ、インドなど50か国以上の主要国が対等に関与し、標準化を共同で進める場となっています。
WP.29で採択されるUN規則はEU規則とは別のものであり、EUはそれを積極的に採用している地域の1つということです。
また、WP.29は欧州委員会の下部機関ではなく、あくまで国連の機関であり、EUもその構成国の一つとして代表を持って参加しているということになります。
この記事を共有する