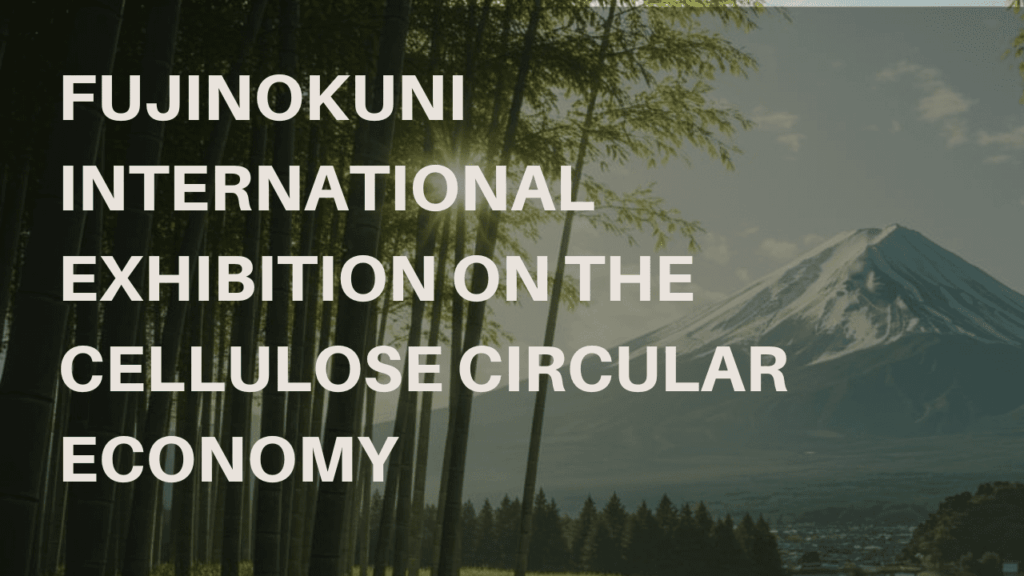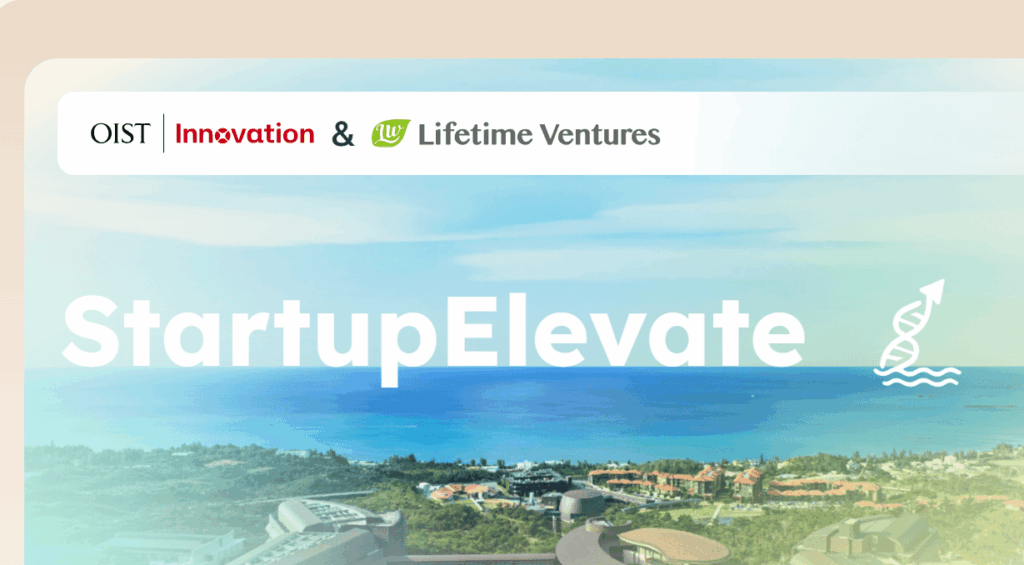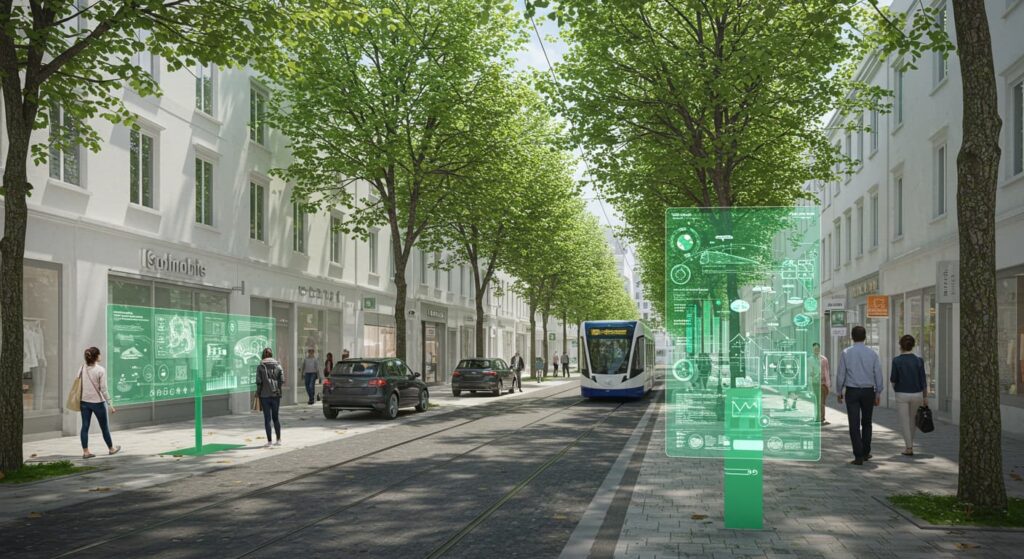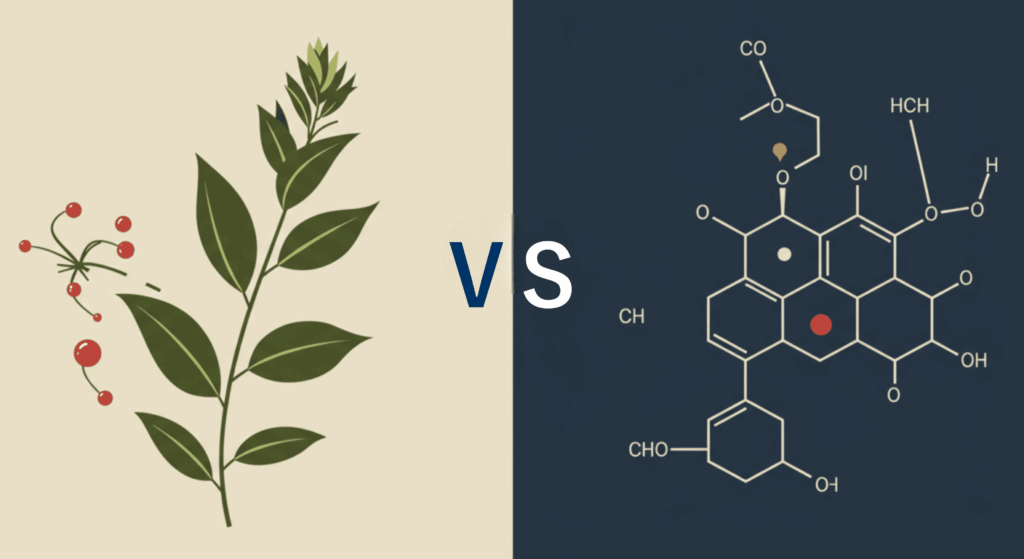バイオシリカのタイヤ応用と広がる可能性 ― 稲殻から未来素材へ
2025-08-17

自動車用タイヤは、天然ゴムや合成ゴムに加え、カーボンブラックやシリカなどのフィラーを組み合わせて作られる複合材料です。これらは燃費、耐摩耗性、ウェットグリップといった性能を支える重要な要素です。近年、化石資源への依存を減らすために「バイオ由来フィラー」が注目を集めています。その代表格が「バイオシリカ」です。
バイオシリカとは何か
バイオシリカは、稲殻や小麦わら、トウモロコシの茎などの農業残渣や藻類などを原料とする、再生可能なシリカです。高純度で細かい粒子径を持ち、比表面積も大きいため、従来の沈降シリカに代替可能な機能を示すとともに、環境適合性の高さが大きな特長となっています。
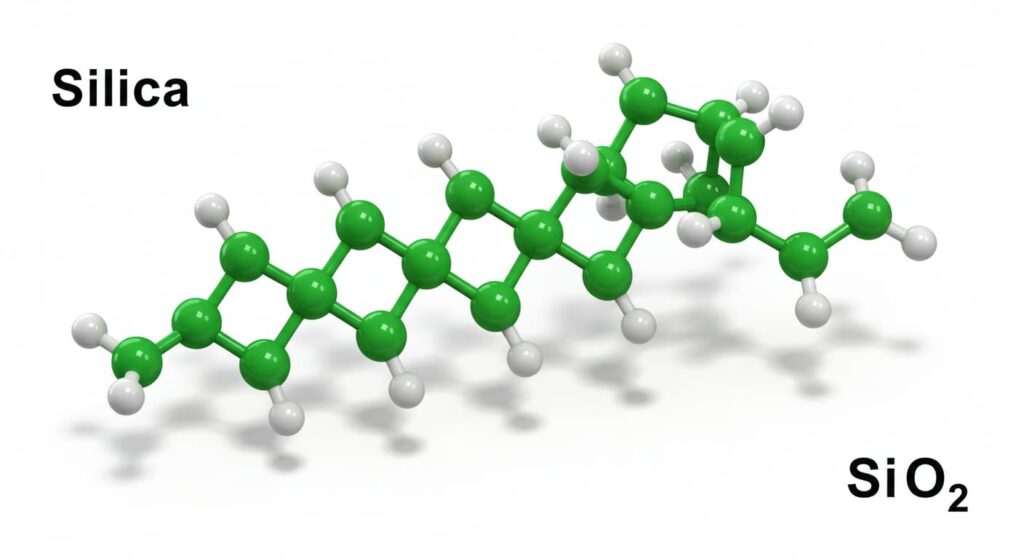
バイオシリカの主な種類
稲殻やサトウキビのバガスといった農業副産物から得られるバイオシリカは、合成シリカに代わる持続可能な原料として注目を集めています。製造方法や原料によって粒子径や表面特性が異なり、それぞれがタイヤ用途における性能発現に大きな影響を与えます。本章では、バイオシリカの種類と特性を整理します。
稲殻灰シリカ:世界的に豊富な稲殻を原料とし、燃焼や酸処理を経て製造されます。粒子が細かく、ゴム補強材として高い適性があります。
籾殻由来シリカ:焼成条件により粒径や比表面積が変化し、機械的特性に影響を与えます。
藻類由来シリカ:珪藻の多孔質殻を活用し、独自の微細構造を持ちます。高機能材や医療用途への展開が期待されています。
その他農業残渣由来シリカ:竹、小麦わら、トウモロコシ茎など、地域資源を活用する事例が増えています。
タイヤでの応用メリット
シリカは低燃費タイヤに不可欠なフィラーですが、その供給は従来、化石資源由来に依存してきました。バイオシリカを用いることで、二酸化炭素排出削減や資源循環への貢献とともに、ウエットグリップ性能や耐摩耗性の向上が期待できます。ここでは、具体的な性能面でのメリットを解説します。

| 性能軸 | 内容 | 効果・意義 |
|---|---|---|
| 低転がり抵抗の実現 | シリカとポリマーとの強い相互作用によりエネルギーロスを低減 | 自動車の燃費改善、EVの航続距離延長に寄与 |
| ウェットグリップ性能の向上 | 親水性を持つため濡れた路面でも摩擦を維持 | ブレーキ性能の強化、安全性の向上 |
| 摩耗特性の改善 | 単独ではカーボンブラックに劣る場合もあるが、併用で性能補完可能 | 耐摩耗性と低燃費性の両立が可能 |
| 環境対応 | 稲殻など農業残渣の有効利用、廃棄物削減、カーボンフットプリント抑制 | サステナビリティ戦略や環境規制への適合、企業イメージ向上 |
最新動向
各社が稲殻由来や廃棄物由来のシリカを活用し、低転がり抵抗・CO₂削減を実現するタイヤを次々と発表しています。Pirelliは市販化で先行し、Continentalも導入を加速。SolvayとHankookは循環型シリカで協業し、欧州で低炭素生産を計画しています。
Pirelliが世界初となる「70%以上がバイオベース/リサイクル素材」で構成された市販タイヤを発表しました。その中で、トレッドゴムには稲殻由来シリカが使用されています。
Continentalも、持続可能なサプライチェーンの取り組みとして、ライスハスクアッシュ由来シリカの導入を進めています。これは転がり抵抗低減やCO₂排出削減に寄与するとしています。
SolvayとHankook(韓国)が、バイオ由来かつ廃棄物由来の「サーキュラーシリカ」の共同開発でMOUを締結。量産化に向けた動きが進行中です。
Solvayはイタリア・リヴォルノの工場で世界初となるヨーロッパ向けのバイオサーキュラー型高分散シリカの生産を計画中で、製造プロセス全体でのCO₂排出を約50%削減できる見込みと発表しています。
タイヤ以外の幅広い応用
バイオシリカはタイヤだけにとどまらず、プラスチックやコンクリート補強材、化粧品や医薬品の添加材など、多様な産業分野での利用が検討されています。軽量化や機能性付与といった観点で、既存のシリカ市場を大きく変える可能性を秘めています。応用分野の広がりについて見ていきます。

| 分野 | 応用方法 | 期待される効果・特性 |
|---|---|---|
| プラスチック補強材 | ポリプロピレン(PP)やポリエチレン(PE)に添加 | 剛性・耐熱性の向上、タルクやガラス繊維の代替、軽量化による成形性改善 |
| 建材 | コンクリートやモルタルに混合 | 圧縮強度・耐久性の向上、セメント使用量削減によるCO₂排出低減 |
| 塗料・インク | マット感の付与、耐候性の改善 | 高機能塗料(光触媒活性など)の開発、紫外線耐性や色あせ防止 |
| 医療・化粧品 | 藻類由来シリカを薬剤キャリアや吸着剤として利用 | 薬物送達システム(DDS)、化粧品の感触改良・皮脂吸着、自然由来成分による安全性向上 |
産業利用における課題
魅力的な特性を備えたバイオシリカですが、産業化にはコストや品質安定性、供給量確保といった課題が存在します。また、カーボンブラックや合成シリカに比べたときの加工適性や分散性についても研究途上です。本章では、実用化に立ちはだかる壁と、それを乗り越えるための取り組みについて整理します。
将来の可能性
短期的には稲殻由来シリカの導入が進み、プレミアムタイヤ市場での採用が増加すると予想されます。
中期的にはEV向けタイヤにおける採用が拡大し、航続距離性能と耐久性の両立に寄与すると期待されます。
長期的には、バイオ炭やセルロースナノファイバーとの組み合わせにより、完全バイオマス系タイヤの実現に向けた研究開発が加速するでしょう。さらに、粉じん規制の強化に対応する生分解性コンポジットの開発にもつながると考えられます。
おわりに

バイオシリカは、稲殻や藻類といった自然由来資源を活用し、持続可能性と高性能を両立できる素材です。タイヤにおいては低燃費化やウェット性能の向上を実現し、環境規制対応にも有効です。また、プラスチックや建材、塗料、医療といった分野でも応用の広がりが期待されます。
今後は製造コストの低減や品質安定化、界面制御技術の高度化が進むことで、バイオシリカは社会に広く浸透していくでしょう。持続可能な素材としての可能性は極めて大きく、次世代の材料産業を牽引する存在になると考えられます。
バイオシリカの用途開発に関する問い合わせ
バイオシリカを活用した材料開発や応用検討に関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。用途開発・共同検討も承っております。
この記事を共有する