タイヤ素材開発のリアル:市場・難しさ・材料進化・規制対応まで
2025-06-02

カーボンニュートラル、EV化、マイクロプラスチック規制──自動車産業が大きな転換期を迎える中、「タイヤ」に求められる役割も変わりつつあります。
その中核にあるのが、タイヤを構成する「素材」。
路面との接点であり、車両性能や環境負荷に直結するタイヤ素材は、今や単なる部品材料ではなく、モビリティと地球の未来を左右する“戦略的技術領域”といえるでしょう。
世界のタイヤ素材市場:なぜいま注目されるのか
世界のタイヤ市場は年間2,000億ドル以上。その中で素材分野──合成ゴム、天然ゴム、補強材、加工助剤、加硫促進剤など──は300〜500億ドルに達する重要なカテゴリです。今後は特にEVや低燃費車の増加により、転がり抵抗の低減や軽量化、静粛性向上といった性能ニーズが高まる見通しです。
また、サーキュラーエコノミーやREACH規制などの影響により、持続可能な素材の使用やLCA評価への対応も求められています。素材メーカーにとって、タイヤは安定市場であると同時に、革新性を問われる競争領域でもあるのです。

タイヤの種類と求められる性能の違い
タイヤは用途に応じて特性が大きく異なります。代表的な種類と要求性能を以下に示します。タイヤは単一構造ではなく、用途や車両種別によって求められる性能が大きく異なります。主な分類は以下のとおりです。
| 種類 | 主な用途例 | 求められる性能 |
|---|---|---|
| 乗用車用 | 通常・EV車 | 低燃費性、静粛性、快適性、耐摩耗 |
| 商用車用 | トラック・バス等 | 耐荷重性、耐熱性、長寿命 |
| モータースポーツ | F1・ラリーなど競技用 | 極限のグリップ、高温対応、剛性 |
| 冬用 | スタッドレス・スノー | 低温柔軟性、氷雪路での制動性 |
| オフロード | SUV・建機 | 耐パンク性、泥はけ、接地性能 |
EV向けタイヤでは、車両重量が重く瞬時のトルク変化も大きいため、特に耐摩耗性と転がり抵抗のバランスが重要です。こうした条件に最適化するには、素材単体の性能ではなく、コンパウンド設計・タイヤ構造・車両制御との統合的開発が求められます。
タイヤ用途開発の難しさ・特殊性
タイヤ用素材開発は、汎用ゴム製品や工業用樹脂の開発とは異なる難しさを持ちます。
加硫を経て最終物性が確定するため、予測と実際にギャップが生じやすい
異なる部位(トレッド、サイドウォール等)ごとに異配合が必要
高荷重・高温・摩擦・屈曲といった過酷環境下で使用される
構造設計・車両特性・運転条件との複合的な関係が支配的
また、各部位の相互作用によって性能が決まるため、素材単体での試験では十分な評価が困難です。タイヤメーカーの設計者やCAEとの密な連携が不可欠になります。
タイヤ用途開発のロードマップ
素材が実際にタイヤへ採用されるまでには、以下のような工程があります。
このプロセスは、短くても18〜24カ月、長ければ5年以上を要します。量産採用までの時間軸と予算、技術リソースを中長期視点で確保する必要があります。
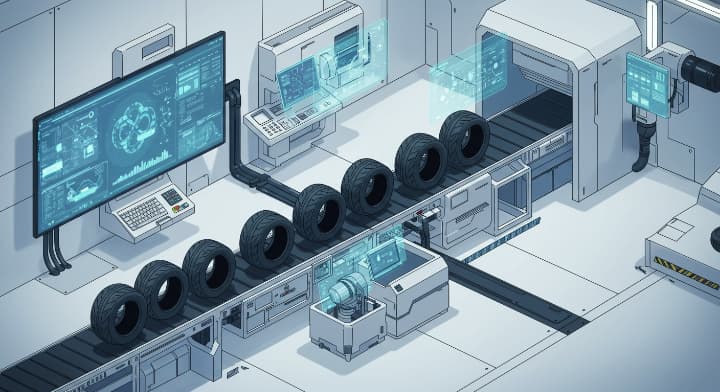
| No. | 工程段階 | 主な内容・目的 |
|---|---|---|
| ① | 配合設計 | 分子構造・配合比の検討、助剤選定 |
| ② | ラボ性能評価 | DMA、引張、摩耗、加硫特性などの基礎物性評価 |
| ③ | 試作・加工検討 | 混練・押出・加硫条件の最適化 |
| ④ | タイヤ成形・実走行試験 | 転がり抵抗、ウェットグリップ、騒音の実走行での性能評価 |
| ⑤ | OEM・メーカー調整 | 顧客要求に基づく仕様の調整・承認取得 |
| ⑥ | 工業化・量産化 | スケールアップ、生産安定性・供給体制の構築 |
成功確率とハードルの高さ
タイヤ用途で新素材が量産採用に至る確率は、他用途と比べても圧倒的に低く、10案件に1件以下とも言われます。タイヤメーカーごとの評価基準に加え、車種別・季節別での適合確認が必要であり、コストやLCA視点から不採用となるケースも多々あります。
また、サンプル採用されたとしても、実車両テストで期待通りの性能が出ない、成形不良が生じるといった“壁”が頻発します。これらを乗り越えるには、評価プロセスにおける定量的な相関(ラボ物性と実走行性能の関係)を構築し、タイヤメーカー側と開発初期から戦略的に連携することが重要です。
単独開発の限界と協業の必要性
素材メーカーが単独でタイヤ素材開発を進めるには、コスト・ノウハウ・試験設備のいずれも不足しがちです。特に、タイヤ製造用の金型・試験ライン、タイヤ構造設計の知見がなければ、最終性能にたどり着けません。
実際の成功事例では、タイヤメーカーや自動車OEMとの共同開発契約、PoC試験への参加、LCA情報の共有などを通じて、評価と採用までを一体化させています。研究開発型企業であっても、タイヤ業界特有の流れを把握した外部アドバイザーやパートナー企業との連携は欠かせません。
タイヤ材料の進歩:技術革新と環境適合

近年は「性能」と「環境」の両立を前提とした素材開発が加速しています。
さらに、フィラー界面設計やナノ複合材料による機能性向上も研究されています。欧州を中心にLCA算定の義務化が進んでおり、「機能+環境スコア」で提案できる素材が選ばれる時代に入っています。
| 材料名 | 特長・目的 |
|---|---|
| 高分散シリカ | 低転がり抵抗とウェットグリップの両立 |
| バイオベースSBR/BR | 石油依存低減を目指す環境配慮型合成ゴム |
| CNF(セルロースナノファイバー) | 高補強性と軽量性の両立を実現 |
| 廃タイヤ由来リサイクルフィラー | 循環型原料の活用による持続可能性の向上 |
タイヤに使われる代表材料
タイヤはゴム部分だけでおよそ15種類以上の素材から構成されます。
各材料の組み合わせと配合技術が、タイヤ全体の性能とコストを左右します。素材メーカーにとっては、物性の優位性だけでなく、成形性・加工安定性・歩留まり改善といった実装レベルの貢献が鍵となります。
| 種別 | 材料名 | 主な機能 |
|---|---|---|
| ゴム | SBR、BR、NR | 耐摩耗、低発熱、グリップ性 |
| フィラー | カーボンブラック、シリカ | 補強、燃費、ウェット性能 |
| 加硫系 | 硫黄、CBS類、ZnO | 架橋促進、加硫反応補助 |
| 添加剤 | ステアリン酸、6PPD | 劣化防止、加工性補助 |
| 樹脂類 | スチレン系、フェノール樹脂 | グリップ、冬性能補助 |
| 分散剤 | 高分子系、脂肪酸誘導体 | シリカ分散向上 |
欧州の粉じん排出規制:TWP規制の衝撃
2020年代以降、欧州委員会(EC)は「タイヤ摩耗粒子(TWP: Tyre Wear Particles)」による環境汚染問題に注目しています。
TWPは、粒径がPM2.5〜PM10以下のマイクロプラスチックとして、水域や空気中に拡散することが報告されています。
これを受け、欧州では2025年以降のタイヤラベリング制度へのTWP排出性能の導入が予定されています。
関連記事
CO2排出や燃費に次ぐ“第三の環境指標”となる可能性
この動きは日本や北米にも波及する可能性があり、今後の素材開発では、TWP対応が避けて通れない競争軸になります。
摩耗量を低減する高耐摩耗トレッド配合
環境無害な摩耗粒子組成(バイオ由来、無毒化)
摩耗測定の標準化とラボ⇔実走間の再現性確保
まとめ:素材が動かすモビリティの未来
タイヤは車の足元を支えるだけではありません。
エネルギー効率、快適性、安全性、そして環境影響を決定づけるプロダクトです。
その性能の多くを担う素材の開発は、単なる改良でなく、未来のモビリティを支える技術革新そのものといえます。

今後のタイヤ用途素材開発は、機能性×環境性×実装性がカギとなります。
素材メーカーにとっては、高度な研究開発力に加え、タイヤ業界の設計思想や規制動向を踏まえた“事業戦略”の視点が不可欠です。
市場が求めるのは、「走る」素材から「社会を前に進める」素材に向けて、長期的ビジョンをもった挑戦が求められています。
タイヤ用途向け素材開発
タイヤ用途向け素材開発に関するご相談・共同開発のご希望がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。技術検討段階から対応可能です。
この記事を共有する

